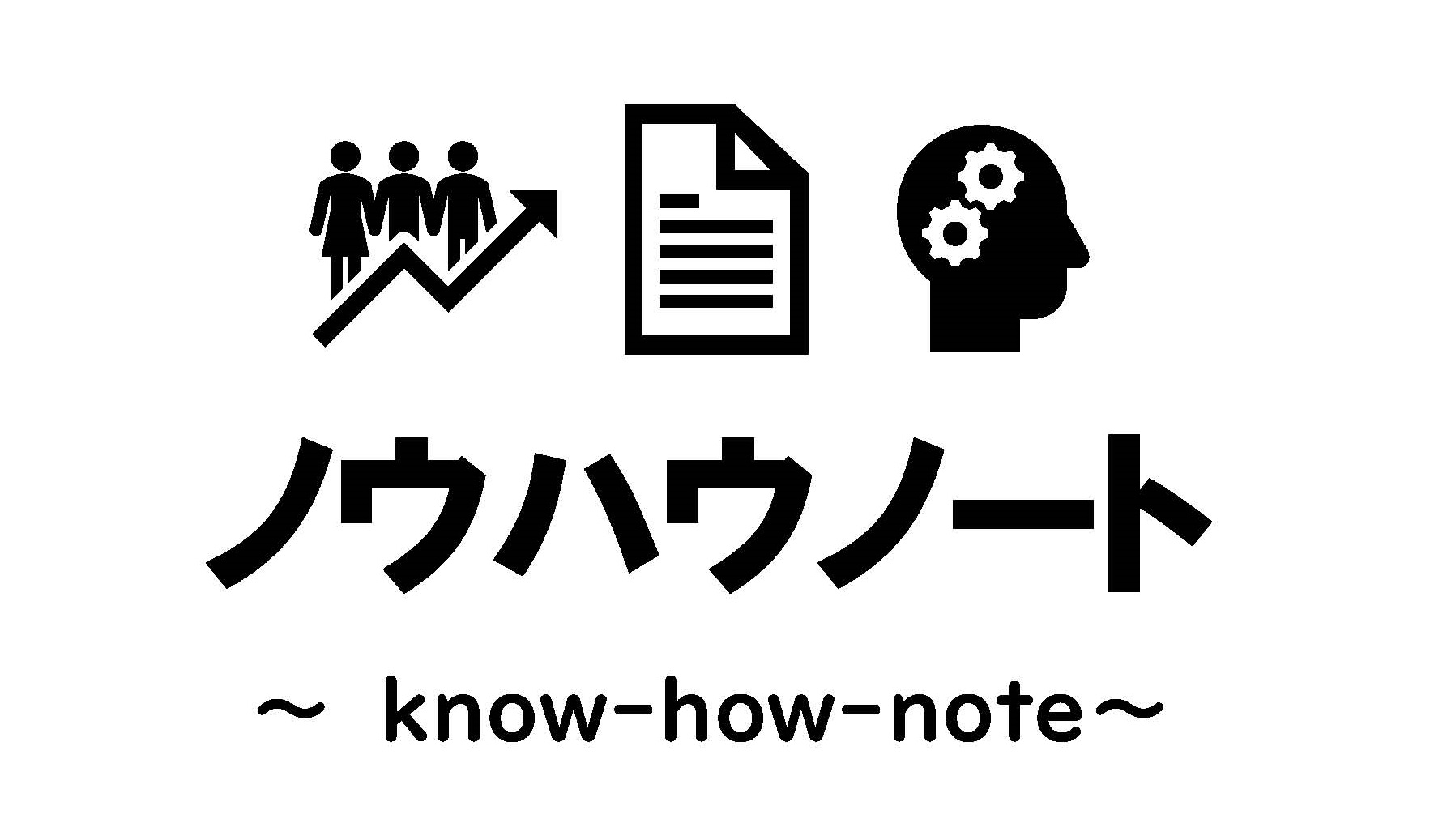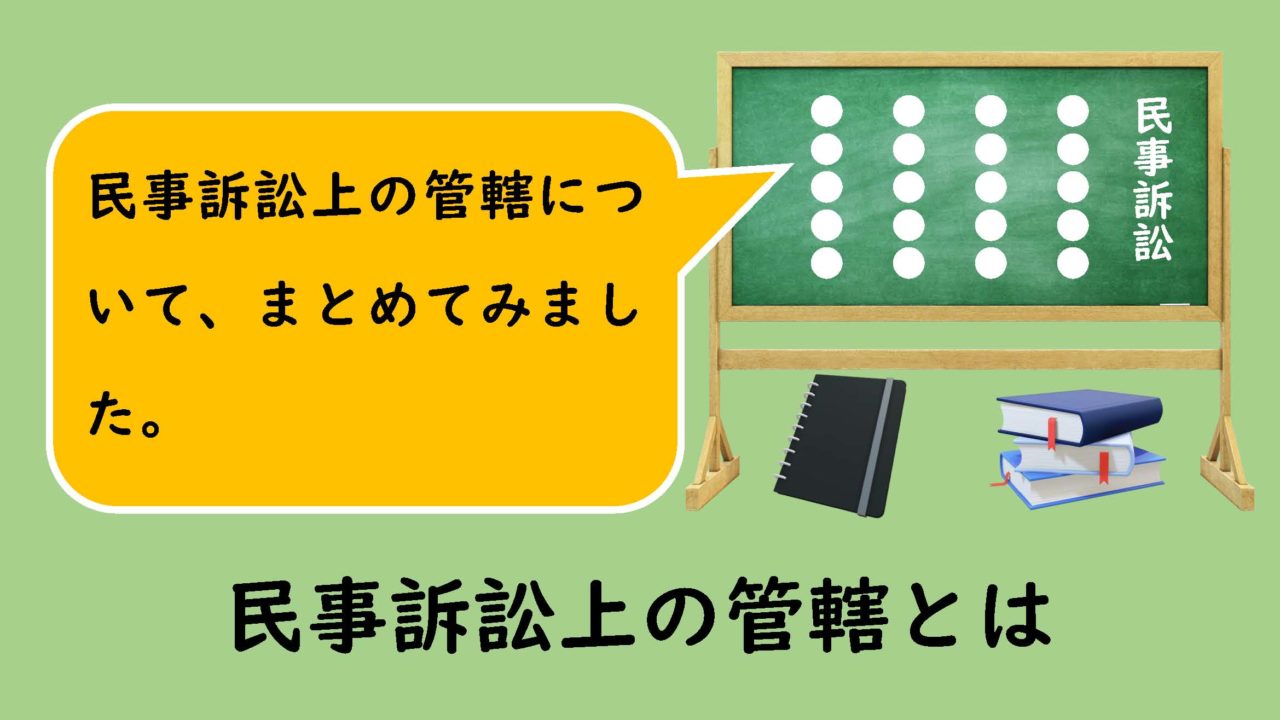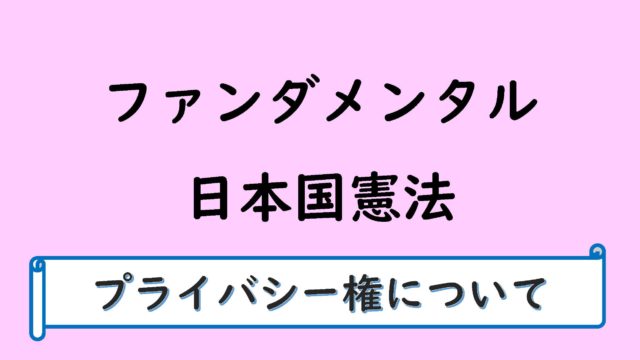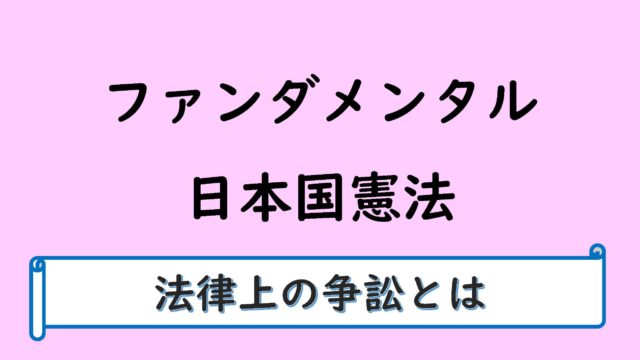裁判所の管轄の意義
日本全国に裁判所が多数ある中で、どの裁判所で当該事件の裁判をすることできるかについては、法律によって定められています。
その定めにより裁判所に与えられた権限のことを管轄権と言い管轄権を有する裁判所ともいいます。
管轄というものは、裁判を行う裁判所を決定づけるものになります。
管轄のいろんな種類が
管轄には、裁判所が持っている作用や機能(受訴裁判所、破産裁判所、執行裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所)の違いによって分類できる職分管轄、第一審裁判の求めるべき金額の価額によって簡易裁判所(~140万円)か地方裁判所(140万0001円~)なのかが定められる事物管轄、全国各地のどの地域の裁判所が担当するのかが定められる土地管轄があります。
その中で、土地管轄については、原則的に被告の住所地、事務所、営業所の所在地が管轄になります(普通裁判籍)。
訴える権利によっては、不動産の所在地、不法行為地、損害の発生地、義務の履行地、登記すべき地に土地管轄が認めれます。
特に特許権に関しては、東京地裁と大阪地裁だけに土地管轄が認められています(特別裁判籍)。
また、いくつかの訴えがある場合に、他の事件と同一の処理のために事件を併合するなどから、その場所に管轄が認められない事件でも、併合先の事件の管轄内で管轄が認められる場合もあります(関連裁判籍)。
複数の管轄の裁判籍がある場合には、いずれかの裁判所によるのかの選択は一次的には原告が選ぶことができます。
合意管轄とは(民事訴訟法11条)
当事者の合意により、第一審の土地管轄と事物管轄については、自由に定めることができます。
ただし、法律が定めた裁判所のみが管轄を有する専属管轄(特許権関連裁判など)や職分管轄については、自由に管轄を合意することはできません。
管轄の合意の要件としては、訴えの提起までに、専属管轄がない場合、不明確で包括的でない合意を、第一審に限り、書面に基づいて合意することができます。
合意当事者とその承継人に限り効力があるので、それ以外の人には合意の効力は及びません。
ただし、裁判所は遅滞をさけるために事件を他の裁判所に移送することができます。
応訴管轄とは(民事訴訟法12条)
本来、管轄の無い裁判所に訴えが提起された場合は、管轄なしとして、別の裁判所へ事件を移送することになります。
その場合でも、裁判所がひとまず、被告の反応を伺うために被告に訴状を送達し、その後、被告が管轄について異議を述べずに訴訟に応じた場合(応訴という)に、公平と迅速の観点から、その裁判所にも管轄を認めることにしています。このことを応訴管轄と言います。
応訴管轄が生じるための要件としては、第一審裁判所において、専属管轄の定めがない場合に限り、被告が管轄違いの抗弁を提出しないまま、弁論手続や弁論準備手続で現実に口頭で弁論や申述した場合に応訴管轄が生じます。
被告が欠席して擬制陳述した場合には応訴管轄は生じません。
専属管轄とは(民事訴訟法13条)
公益の要請から、法律によって特定の裁判所のみに訴えを提起できる管轄を定め、それ以外の裁判所の管轄を排除する管轄のことを専属管轄と言います。
ある種の訴えを提起する場合に、その種類の手続のことを定めた法律の規定に、専属管轄によって訴えを提起をする必要があるする場合には、普通裁判籍、特別裁判籍、合意管轄、応訴管轄に関する規定が全て排除されています。
管轄の有無の調査の主体(民事訴訟法14条)
管轄は訴訟をするための入口要件の一つであるため、当事者からの主張や反論がなくとも、裁判所が自ら管轄の存否について調査する義務を負い(職権調査事項)、訴えが有効なのかを判断する必要があります。
そのため、管轄の調査に必要な証拠調べについては、職権で行うことができます。
管轄を決める時期(民事訴訟法15条)
管轄は、原告が裁判所に訴状を提出したときを基準として定まります。訴えた後に被告の住所が変わっても、管轄は変わりません。
逆に、訴え提起時に管轄がなくとも、その後、管轄違いの移送が確定するまでに何らかの管轄が生じれば、管轄違いの原因は治癒されます。
反訴、中間確認、訴えの変更の場合、それぞれの手続のために新しく訴えをする時に管轄を判定しなおすことになります。