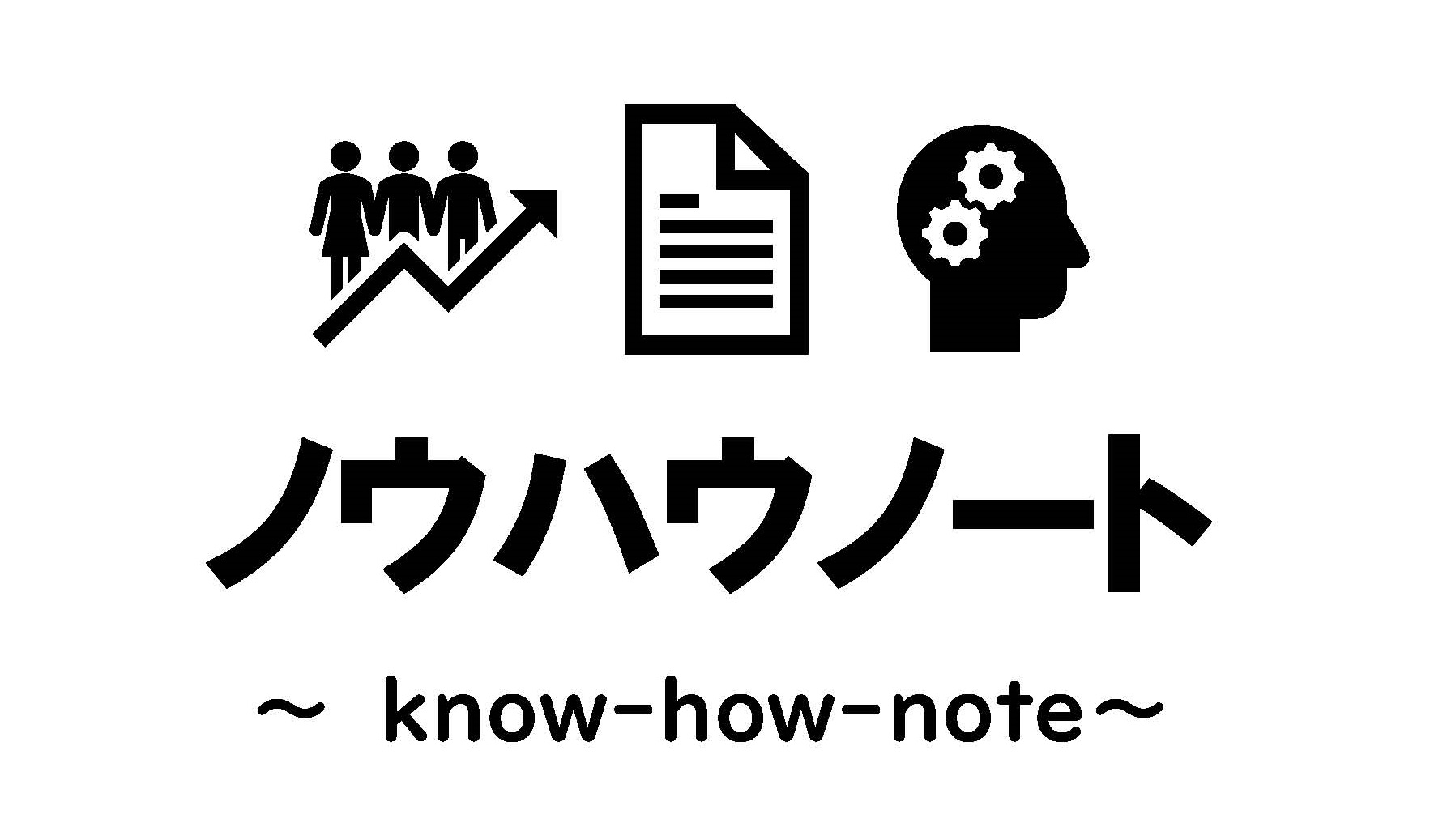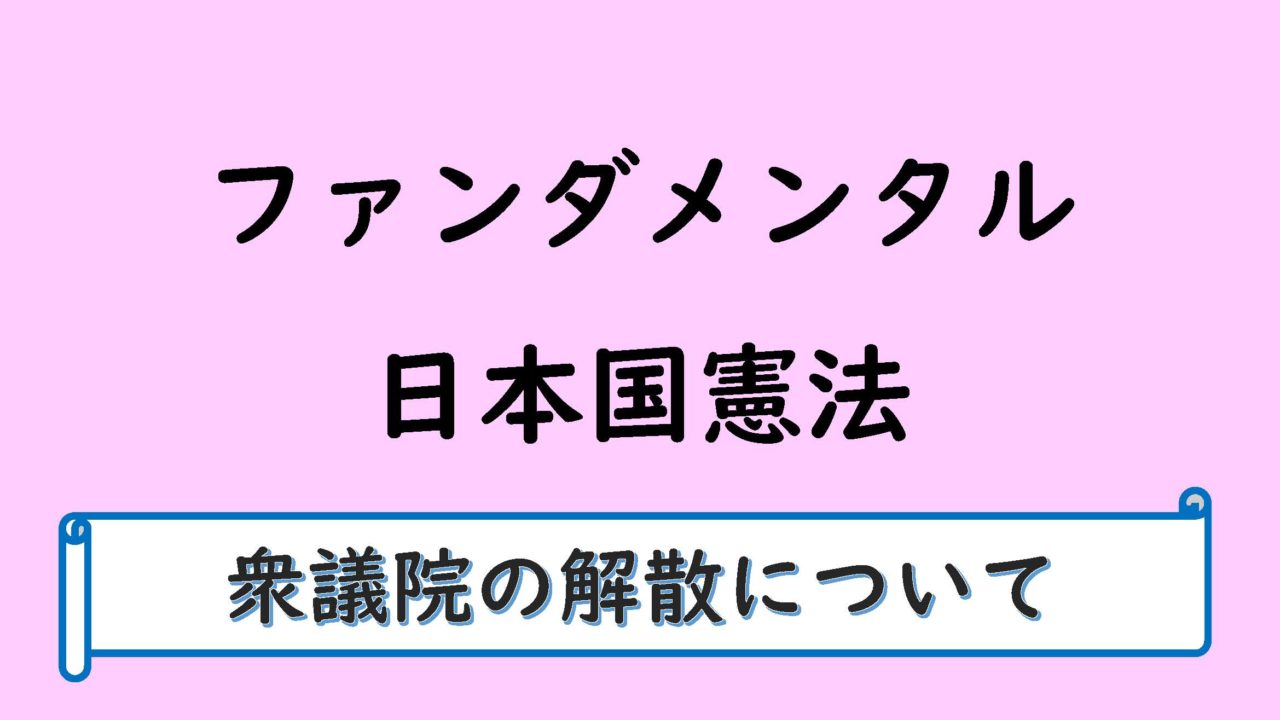衆議院の解散とは
衆議院の解散とは、衆議院の全議員の資格を任期満了前に一斉に失わせる行為です。
内閣と国会とが対立した場合や、重要な政治問題が生じた場合に、衆議院を解散することで、これに続く総選挙(憲法54条1項)により主権者たる国民の意思を問うことが可能であるため、解散には重要な民主主義的な意義があることになります。
解散権の憲法上の根拠
憲法69条は、衆議院で内閣の不信任案を決議した場合及び信任決議を否決した場合に衆議院の解散ができることを示していますが、解散権を行使する主体や解散の要件については明確に規定しておりません。
衆議院の解散は、天皇が「内閣の助言と承認」を得て行う国事行為のひとつとされており(憲法7条3号)、形式的には衆議院を解散する主体は天皇です。
ただ、天皇は国政に関する権能を有しない(憲法4条1項)ため、実質的な解散権の行使主体は誰であるのかが不明確なのです。
憲法69条には、「衆議院が解散されない限り」との文言が存在していますが、この憲法69条の文言は、解散が行われる場合の1つをただ単に例示したにすぎないとも思えます。
そこで、衆議院の解散権を行使する場面は、憲法69条に限られるのか、それとも憲法69条以外にも政治的な判断で衆議院を解散できるのか、学説上、様々な見解が主張されています。
解散権の根拠をめぐる学説
憲法69条説
解散権行使の主体は内閣で、内閣による衆議院の解散権の行使は、憲法69条が規定するとおり、内閣不信任議決があったときにのみ、解散が許されるとする学説です。
憲法7条説(通説・実務)
憲法69条以外の場合でも解散権の行使が内閣にできるとする学説です。
衆議院の解散は天皇が行う国事行為とされていますが、天皇は国政に関する権能がないため、憲法7条により天皇に「助言と承認」を行う内閣に実質的な解散権の行使の主体があるとする学説です。
この学説に従うと、解散権行使の主体は内閣であり、憲法7条3号は解散について特別な制限を規定していないので、政治的な妥当か否かは別として、法律上はいつでも解散権を行使することができます。
ただし、天皇の国事行為という形式的な行為に対しての助言と承認に実質的な権能を盛り込むことは困難だとの批判もあります。
制度説
解散権の根拠を憲法上の特定の条文ではなく、議院内閣制という制度自体に求める学説です。
憲法は議院内閣制を採用していますが、議院内閣制では内閣に自由な解散権が認められるのが、世界の通例であるということを根拠としています。
この学説に従うと、解散権の主体は内閣で、内閣はいつでも解散権の行使ができることになります。
ただし、世界の議院内閣制の体制も一様ではなく、議院内閣制そのものから当然に内閣に自由な解散権があるとの結論は難しいのではとの批判がされています。
衆議院の自律的な解散
解散権行使の根拠についての学説は諸説ありますが、解散権行使の主体が内閣であることは一致しています。
では、立法機関たる衆議院自身が内閣の関与なく、議院の議決によって、自律的に解散することは認められるのでしょうか。
自律的な解散を認める憲法上の根拠がないことや、議員の除名処分には議会の3分の2以上の賛成が要求される(憲法58条2項但書)ことから、解散権を過半数の議決だけで行い、少数派の議員の地位を奪うことになるため、自律的な解散は許されないと考えられています。
これまでの歴史の中でも衆議院が自律解散を行った実例はありません。
解散権における日本政府の立場
戦後GHQは、解散権の根拠は憲法69条の場合に限られると解釈しており、日本国憲法下で行われた初めての解散は、与野党の話し合いで、内閣不信任案を可決するという「なれ合い解散」でした。
その後の第2回目の解散は憲法7条に基づき行われ、以降は、憲法7条による解散が運用として定着しています。
日本政府の見解も、解散権の根拠は憲法7条であるとしています。
その後、裁判の場では、第2回目の解散により議員資格を失った議員が、解散が憲法に反し無効であると主張して、衆議院議員としての資格の確認と任期満了までの歳費の支払を求めて訴えを提起しました。
これに対して、最高裁は、「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為で、法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にある。
衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合、裁判所の審査権の外にあるといわなければならない。」と述べ、いわゆる統治行為論により憲法判断を避けました(最高裁判例:昭和35年6 月8日「苫米地事件」)。
解散権行使の政治的な限界
解散権の行使に関する様々な学説であっても、内閣は、法的にはいつでも自由に衆議院の解散を決定することができます。
ただし、内閣による解散権が恣意的な運用や濫用的な行使がされないように、解散権の政治的な限界があり、解散に続く総選挙によって国民の審判を求めるにふさわしい理由があることが必要だとされています。
そのため、次のような場合に限って解散権を行使できると考えられています。
具体的には、
①衆議院で内閣の重要案件が否決・審議未了の場合
②政界再編で内閣の性格が基本的に変化した場合
③選挙の争点になる新たな重大政治的課題の発生
④内閣が基本政策を根本的に変更する場合
⑤議員の任期満了時期が接近している場合
その他に解散の妥当性が問題となる場面として、違憲状態の定数配分規定のまま解散に踏み切ることで、続く総選挙で正しい民意が反映されず、民主的意義が失われる場合や、衆参同日選挙を目的とした解散で二院制(憲法42条)の趣旨が失われる場合にその妥当性が問題となっています。
解散後の手続
国会の会期中に衆議院が解散されると、参議院は同時に閉会(憲法54条2項)となります。
そして、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、総選挙の日から30日以内に国会が召集され(憲法54条1項)、内閣は総辞職をしなければならないと決められています(憲法70条)。